1990年代初頭、グランジの熱狂が世界を席巻した後、ロックは新たな方向へと進化を遂げていった。
ニルヴァーナの『ネヴァーマインド』(1991)がメインストリームを揺るがしたのを皮切りに、音楽シーンは「オルタナティヴ」という新しい価値観を掲げ、従来の商業主義的ロックからの脱却を模索していく。
この時代のロックは、一言でいえば「多様性の爆発」だった。
グランジ以降の混沌と再生
グランジが終焉を迎えた後、アメリカとイギリスでは、それぞれ異なる形でロックの再構築が始まった。
アメリカでは、パール・ジャムやスマッシング・パンプキンズがグランジの遺伝子を受け継ぎつつ、よりスケールの大きなサウンドを追求。
一方、イギリスではブリットポップが勃興し、オアシスやブラーが「日常とポップの美学」を掲げてロックを再び大衆の手に取り戻した。
この「ポスト・グランジ期」の特徴は、どのアーティストも“ロックとは何か”を改めて問い直した点にある。
かつてのロックが「反体制」を叫んでいたのに対し、90年代後半のロックは「個人の感情」「社会との距離感」を見つめ直す方向へシフトしていった。
オルタナティヴという“選択肢”の拡張
「オルタナティヴ(Alternative)」という言葉は、「主流ではない」「代わりの」という意味を持つ。
だがこの時代、オルタナティヴは単なるジャンル名を超え、「音楽を自由にする思想」そのものとなった。
レディオヘッドの『OK Computer』(1997)はその象徴だ。
テクノロジー社会への不安と孤独を繊細なサウンドで表現し、ロックが持つ叙情性と実験精神を融合。
その後のミュージシャンたちに「ロックはまだ進化できる」という確信を与えた。
また、アメリカではR.E.M.やベック、フーファイターズが多様なスタイルを展開し、インディーシーンとの距離を縮めた。
この頃、インターネットやMTVの普及もあって、音楽はより個人化・多層化。
「オルタナティヴ=自分の感じ方を肯定するロック」という価値観が広がっていった。
インディー・ロックの台頭とDIY精神の復活
90年代後半から2000年代にかけて、ロックは再び地下から盛り上がりを見せる。
シアトルやロサンゼルス、ロンドン、ニューヨークなどの都市では、インディー・レーベルが若手バンドを次々と発掘。
ザ・ストロークス、アークティック・モンキーズ、モデスト・マウスといったバンドが、オルタナティヴの新しい顔として登場した。
彼らの共通点は、洗練されたサウンドの裏にある“DIY精神”だ。
自分たちの手で録音し、ネットで発信し、ファンと直接つながる。
大手レーベルや商業主義に頼らない姿勢は、まさにパンクの精神を現代に甦らせたものだった。
オルタナ以降の「個」の時代へ
2000年代後半以降、オルタナティヴの概念はさらに拡張され、
ボン・イヴェール、フローレンス・アンド・ザ・マシーン、ミューズ、アーケイド・ファイアといった多彩なアーティストたちが登場した。
電子音楽やクラシックの要素を取り入れつつも、彼らの音楽には“人間らしさ”が宿っている。
ロックはもはや「ギターを鳴らす音楽」ではなく、「心の叫びを形にする手段」へと変わった。
その意味で、オルタナティヴの精神は現代のポップスやヒップホップにも息づいている。
ジャンルを越えて、自由な表現を追い求めるアーティストたちこそ、今のロックの継承者なのかもしれない。
まとめ ― ロックは“形を変えて生き続ける”
グランジ以降のロックは、商業的な枠組みから解放され、
アーティスト一人ひとりの「個性」や「感情表現」に焦点を当てるようになった。
オルタナティヴという言葉は、「変わり者」や「異端者」を意味するが、
それは同時に、「新しい時代を切り拓く力」を象徴している。
いま、ストリーミング時代の音楽はますます多様化している。
だがその根底には、90年代のオルタナティヴ・ロックが築いた「自由で、正直な音楽を」という精神が確かに生きている。
ロックは死なない。それは、常に“変わり続ける”からだ。
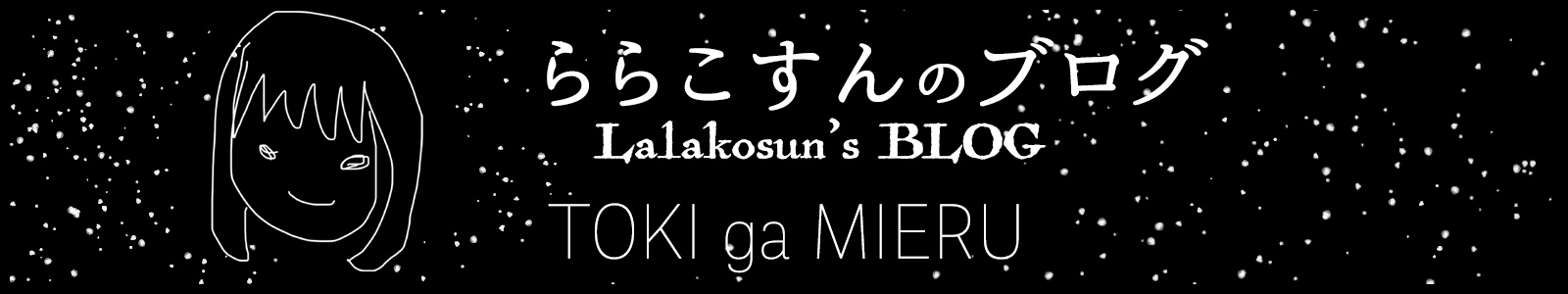
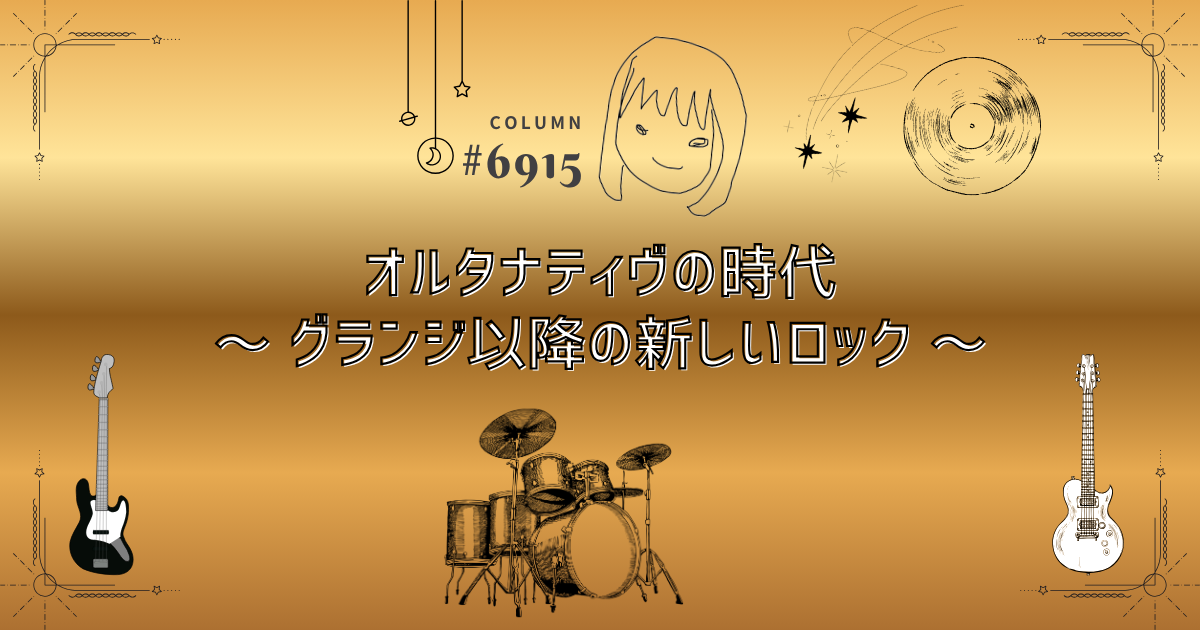
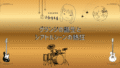
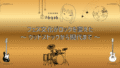
コメント