ステージ4の乳がんという診断を受けた私は、「これからどこで、どんな治療を受けていくのか」という大きな課題に直面しました。
最初に診てもらったクリニックではステージ4の乳がん治療はできないとのことで、転院することになり、どこの病院で治療をするのかを決めて、紹介状を出してもらうことになりました。
けれども、いざ病院を選ぶとなると、想像以上に迷いました。
がんの治療は一度始めると長い付き合いになりますし、治療方針によって生活の仕方も大きく変わってしまいます。
当時の思考の整理も含めて、病院選びについて書き残しておきたいと思います。
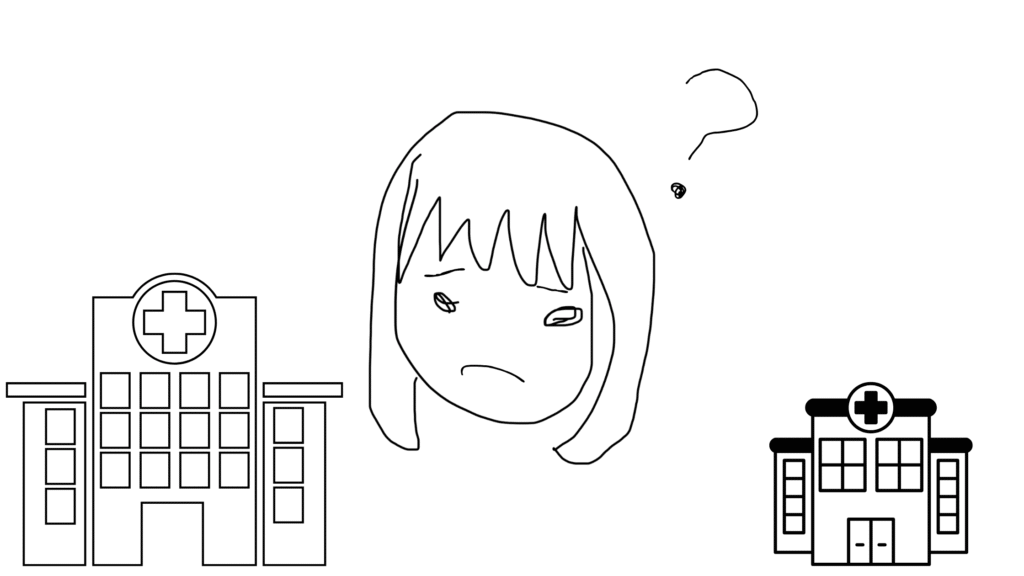
病院選びでの迷いと焦りと・・・
私が住んでいるのは東北の田舎町なので、病院選びと言っても、そんなに選択肢はなく、候補として挙がった病院は3つでした。
①隣県の病院
元々受診していた病院の先生から勧められた、隣県にある大きな総合病院。
そこは乳がん症例数も多く、認定看護師も在籍しており、緩和ケアもある。
ただ、隣県となるため、通院に車で片道2時間弱かかる。②県内で症例数の多い病院
県内では一番症例数が多い総合病院。
実家からも近いので、何かあった場合には実家に寄ったり、泊まったりということもできるメリットもあります。
だけど、県内であっても通院に車で片道1時間半はかかる。③家から一番近い病院
症例数はそこまで多くはないものの、治療を受けられる、家から一番近い総合病院。
通院に車で片道30分。最初は元々受診していた病院の先生から勧められたことや症例数の多さから、隣県にある大きな総合病院で治療を受けたいと思いました。
しかし、通院に片道2時間弱かかるため、小さい子どもを育てながら、長期にわたる治療を続けていけるのかを考えると、単純に「症例数が多いから」という理由だけでは決められませんでした。
さらに、乳がんはサブタイプによって治療法が大きく異なります。
私はトリプルネガティブ乳がんと診断されていたため、抗がん剤治療が中心になることは理解していましたが、「どの薬を、どのタイミングで使うのか」は病院や医師の方針によって違うと聞き、不安が募りました。
ですが、どの病院で治療をするかを迷ってる間にも、しこりはどんどん大きく硬くなっていっていて、早く病院を決めて、少しでも早く治療を始めないといけないという強い焦りも感じておりました。
そういう焦りもあり、隣県の大きな総合病院への紹介状を出してもらい、予約をとってもらいました。
治験という選択肢
紹介状を持って隣県の病院を受診したのは、既に3月の下旬でした。
ここの病院の先生は説明がとても分かりやすく、この先生に診てもらいたいなと思える先生でした。
ですが、隣県から通うことになるのを心配されました。
この後、抗がん剤治療が始まり、副作用がでてる中、車での通院は大丈夫ですか?と聞かれました。
この時点では副作用がどんな感じなのか全く想像もできず、副作用でてる中の車での通院にとても不安を覚えました。
また、ここの病院の先生から、あらためて検査結果や今の状況についての説明を受けました。
最初に告知を受けた時はショックのあまり、きちんと聞けていなかったこともあったと思うので、少し時間が経ったこの時に、あらためて説明を受けられたのは良かったと思いました。
その中で「治験」という選択肢があることを知りました。
治験とは、新しい薬の有効性や安全性を確認する臨床試験のことです。
今後の治療の幅が広がる可能性があり、特に進行がんや再発がんの患者にとっては希望となる場合があります。
ここの病院の先生から私の住む県の大学病院に問い合わせをしていただいて、私が治験を受けられる可能性があるかを確認してもらいました。
しかし残念ながら、当時の私の病状や条件で受けられる治験は、その時点では行っていないとの回答でした。
このとき感じたのは、「治験を受けられるかどうかは、タイミングや条件による」ということです。
希望は持ちつつも、必ずしも誰でも受けられるわけではないのだと実感しました。
遺伝子検査と免疫治療の可能性
実は2月にいろいろと検査をしている中で、前に先生から勧められていたBRCA1/2遺伝子検査も受けてました。
この遺伝子に変異があると、PARP阻害薬という薬が使える可能性が出てくるので、治療方法の選択肢が広がります。
ですが、こちらは陰性でした。
また、隣県の病院を受診時、先生とお話をしている中でPD-L1検査も依頼しました。
これは、免疫チェックポイント阻害薬のひとつである「キイトルーダ(ペムブロリズマブ)」が使えるかどうかを調べるための検査です。
免疫療法は副作用が比較的少なく効果がある人もいると聞き、ぜひ可能性を探りたいと思いました。
こうして検査を進めながらも、「では最終的にどこで治療を受けるのか」という問題は残ったままでした。
病院選びで重視したこと
最終的に私が病院を選ぶときに考えた基準は、大きく分けて以下のような点です。
■症例数や専門性:
トリプルネガティブ乳がんの治療経験が豊富かどうか
■通いやすさ:
子育てをしながらでも無理なく通院できる距離か
■医師やスタッフとの相性:
安心して話せる雰囲気があるか
■サポート体制:
栄養指導や緩和ケアなど、生活面も含めて支援があるかこれらを天秤にかけながら、最初は「症例数の多い隣県の大病院」が候補に上がりました。
しかし、家からの距離や治療の長さ、副作用の中での通院を考えると、現実的に通い続けるのは難しいのではと悩みました。
悩みの中で感じたこと
病院選びをしていた頃、私はまだ治療を開始しておらず、体力的にも気持ち的にも不安定な時期でした。
ネットで病院の評判を調べてたり、同じように病院選びで悩んでる方の体験談を読んだり、同じ病気の方の体験談を読み漁っては焦る…。そんな日々が続きました。
一方で、「どんなに大きな病院に通っても、自分が続けられなければ意味がない」とも感じ始めていました。
家族と過ごす時間や生活のリズムを守ることも、治療を続けるうえで大切なのではないか、と。
まとめ
病院選びは本当に悩ましい問題でした。
症例数が多い病院に行けば安心かもしれない、でも通い続ける現実を考えると難しい。
治験や遺伝子検査、免疫療法の可能性を探りながらも、最終的には「自分と家族が無理なく通える病院」を選ぶことが一番だと気づきました。
次回は、私が最終的に「近くの総合病院で治療を受ける」と決断するまでの経緯について書きたいと思います。
子育てや体調の問題も重なりながら、ようやくたどり着いた選択でした。
※この記事は、筆者個人の体験を記録したものです。
医療・法律・投資などの専門的な助言を目的とした内容ではありません。
必要な判断については、専門家や公的機関の情報をご参照ください。
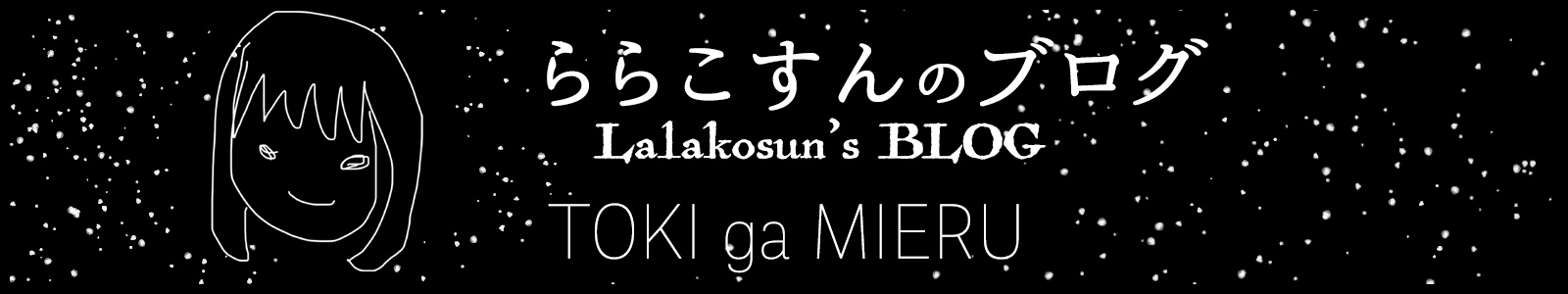

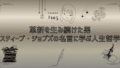
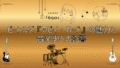
コメント